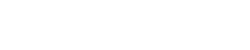本作、横山上野大掾藤原祐定の特徴が顕著に現れ、優れた技量を余すことなく発揮された新刀期の備前鍛冶を代表する同工の優品であります。
脇差 横山上野大掾藤原祐定 備州長船住人 保存刀剣鑑定書
Wakizashi [Yokoyama-kozuke-daijo Fujiwara Sukesada] [N.B.T.H.K Hozon Token]

品番: SWA-080221
価格(Price): 売約済/Sold Out
(消費税込。10万円以上の商品は国内送料込)
品番: SWA-080221
Stock No.: SWA-080221
鑑定書: 保存刀剣鑑定書
Paper(Certificate): NBTHK Hozon Token
国・時代: 備前国・江戸時代中期 寛文頃(1661~)
Country(Kuni)/Period(Jidai): Bizen(Okayama), Middle Edo period about 1661~
刃長 Blade length (Cutting edge) : | 55.5cm(一尺八寸三分半) |
|---|---|
反り Curve(SORI) : | 1.0cm |
元幅 Width at the hamachi(Moto-Haba) : | 3.12cm |
元鎬重 Thickness at the Moto-Kasane : | 0.76cm |
先幅 Wide at the Kissaki(Saki-Haba) : | 2.45cm |
先鎬重 Thickness at the Saki-Kasane : | 0.55cm |
茎 Sword tang(Nakago) : | 生ぶ、勝手下がり鑢目。目釘孔2個。 |
登録 Registration card : | 東京都 |
【解説】
備前長船鍛冶は、通説として吉井川の氾濫により、多くの鍛冶を失ったとされます。被害を逃れた一部のうち、備前祐定一派は、後に新刀期の備前長船鍛冶再興の祖として知られる七兵衛尉祐定らを筆頭として備前刀工の復興に尽力しました。横山上野大掾祐定は、七兵衛尉祐定の子、室町期永正頃の名工、与三左衞門尉祐定より数え六代目とします。
本作は刃長が一尺八寸三分半と刀に迫る長さの脇差で、身幅広く、重ねも確りとし、肉置き豊かで、健全な一振です。鍛えは板目肌が詰み、潤いあって細かな地沸がつきます。刃紋は小沸出来の互の目乱れに僅かに先尖り刃、丁子刃を交えます。同工には末備前、与三左衞門尉祐定らに見られる蟹の爪といわれる刃をしばしば経眼され、本作の刃にも一部、そのような感があります。刃中には、足、葉が入って働きも盛んです。帽子は直ぐとなって小丸に返ります。本作、横山上野大掾祐定の特徴がよく現れ、新刀備前の名工として知られる同工の技を多分に感じる事が出来る一振です。白鞘。銀一重はばき。保存刀剣鑑定書。
備前長船鍛冶は、通説として吉井川の氾濫により、多くの鍛冶を失ったとされます。被害を逃れた一部のうち、備前祐定一派は、後に新刀期の備前長船鍛冶再興の祖として知られる七兵衛尉祐定らを筆頭として備前刀工の復興に尽力しました。横山上野大掾祐定は、七兵衛尉祐定の子、室町期永正頃の名工、与三左衞門尉祐定より数え六代目とします。
本作は刃長が一尺八寸三分半と刀に迫る長さの脇差で、身幅広く、重ねも確りとし、肉置き豊かで、健全な一振です。鍛えは板目肌が詰み、潤いあって細かな地沸がつきます。刃紋は小沸出来の互の目乱れに僅かに先尖り刃、丁子刃を交えます。同工には末備前、与三左衞門尉祐定らに見られる蟹の爪といわれる刃をしばしば経眼され、本作の刃にも一部、そのような感があります。刃中には、足、葉が入って働きも盛んです。帽子は直ぐとなって小丸に返ります。本作、横山上野大掾祐定の特徴がよく現れ、新刀備前の名工として知られる同工の技を多分に感じる事が出来る一振です。白鞘。銀一重はばき。保存刀剣鑑定書。