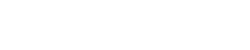本刀は、細川一門で宇都宮藩工の細川義規の一口。同藩抱工としての確かな技量が伺える生ぶ無銘の優刀です。
短刀 無銘 細川義規 保存刀剣鑑定書
Tanto [Mumei Hosokawa Yoshinori][N.B.T.H.K] Hozon Token

品番: STA-100125
価格(Price): 売約済/Sold Out
(消費税込。10万円以上の商品は国内送料込)
品番: STA-100125
Stock No.: STA-100125
鑑定書: 保存刀剣鑑定書
Paper(Certificate): NBTHK Hozon Token
国・時代: 下野国(栃木県)・江戸時代後期 文久頃
Country(Kuni)/Period(Jidai): Shimotsuke(Tochigi)・Late edo period about 1861~
刃長 Blade length (Cutting edge) : | 26.9cm(八寸九分弱) |
|---|---|
反り Curve(SORI) : | 0.2cm |
元幅 Width at the hamachi(Moto-Haba) : | 2.62cm |
元鎬重 Thickness at the Moto-Kasane : | 0.66cm |
先幅 Wide at the Kissaki(Saki-Haba) : | 2.15cm |
先鎬重 Thickness at the Saki-Kasane : | 0.50cm |
茎 Sword tang(Nakago) : | 生ぶ、筋違鑢目、目釘孔1個。 |
登録 Registration card : | 東京都 |
【解説】
細川義規は、下野国(栃木県)を代表する細川一門の刀工です。細川正義(初代)は同一門の祖であり、江戸に出て水心子正秀に鍛法を学び、後に鹿沼に戻り宇都宮藩工となります。細川正義(二代)は、初代正義の嫡男として鹿沼に生まれ、父に倣い水心子門に学び、後に津山藩松平家御抱え工となります。多数の門人育成に尽力し、新々刀期の代表刀工として、師である水心子正秀、同門大慶直胤と並び鍛刀の技に優れて著名であります。本作細川義規は、二代正義の甥にあたり、正平の子。文化十二年(1815年)に下野国鹿沼に生まれます。宇都宮藩刀工として活躍し、水心子系の流れを汲んで備前伝の作風を見ます。また幕末期の下野鍛冶の中でも上手とされ、栃木県指定の文化財に十口の登録を確認できます。
本作体配は、刃長が八寸九分弱、身幅重ね尋常、健全な平造姿の1振です。地鉄は小板目肌が、精良な肌合いで、地沸微塵に付き、棟寄り流れごころを交え、細かに地景が入り、刃寄りには映りが立ちます。刃文は華やかな丁子乱れで、物打ち辺りから乱れの勢いを落として緩やかに湾れ、帽子は地蔵風となり返ります。茎は生ぶ、化粧筋違目となります。本刀は、細川一門で宇都宮藩工の細川義規の一口。同藩抱工としての確かな技量が伺える生ぶ無銘の優刀です。白鞘、金鍍金一重はばき、保存刀剣鑑定書。